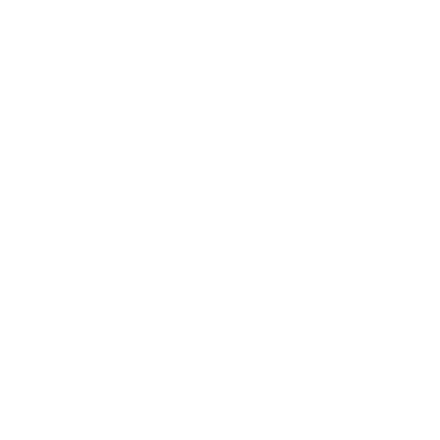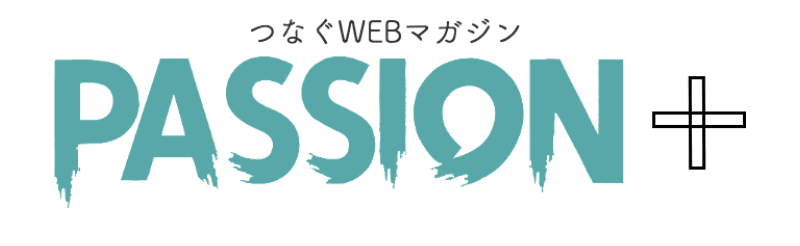COMPANY
(注意)本記事は、金剛株式会社が1991年8月10日に発行した機関誌「PASSION VOL.8」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。
本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。
※logistics:後方業務、兵たん業(調達。貯蔵、輸送、宿営、糧食、交付、整備及び人員、器材、補給品の護送などの業務)
物流活動の改善に対する 大きな期待
ここ数年の物流活動に関する傾向には、かなりの変化が生じてきたように思われます。かつて、企業の物流活動は経営上の付属品として位置づけられ、多くの経営者の頭を悩ませていた時期もあったというのは、今では信じられないほどです。現在では周知の通り、その見方は180°転回し、「物流新時代」とも言われています。
最近特に注目されている物流活動に投資する効果は、原価を引下げ、利潤につながるばかりではなく、顧客へのサービスの手段として有効であり、また、企業の経営戦略の重要な要素となり得るという点だと言われています。
商品の生産、輸送、販売を行ない、それぞれがある程度の機能を果たしてはいるものの、それらの業務間の関連性が希薄で、一貫した「システム」を持たない経営から、マーケティングをし、集めたデータを基に必要な量を生産し、ジャストインタイムの納品を行ない、消費者の手元まで届ける 「システム」を持つ経営への脱皮の成否の如何んは、 物流活動の見直しへの取り組みかた一つに大きく左右されます。 これまで、ともすると合理化の対象として捉えられてきた物流活動を、今後は最も重要な戦略的手段として考えるべき時代になってきたと言えるでしょう。事実、物流活動に思いきった改善の手を加え、プロジェクトを成功させた、 あるいは成功させつつある企業の多くが、更なる大きな発展を実現させているのです。
必須となる物流活動改善への取り組み
戦略経営を実行し、売上げを伸ばし、シェアを 広げた企業も、一朝一夕に成功者となった訳ではありません。戦略経営を成功させるためには、まず数々の障害を取り除かなければならないのです。現在深刻になりつつある「労働力不足」「地価高騰による管理コストの増加」「多品種少量消費」「3K」などの噴出する諸問題。これらの回答としては、「機械による作業の代替」「自動化」「スペース削減」「小口多品種多頻度出荷」「人に負担をかけない作業システム」「作業の効率化」などが挙げられています。
今回は、省力化・リードタイムの短縮・効率経営などを目的とし、物流現場・保管現場の改善を実行された例を紹介させていただきます。読者諸氏の、今後の物流活動改善の傾向についての考察の、参考に供し得れば幸いです。