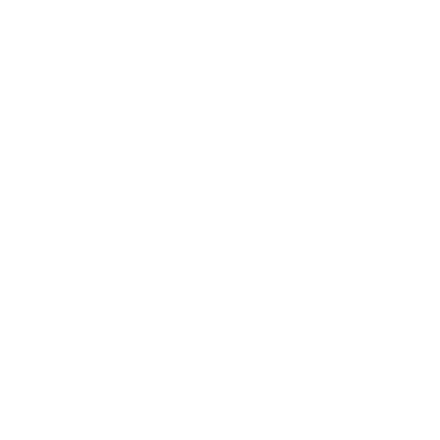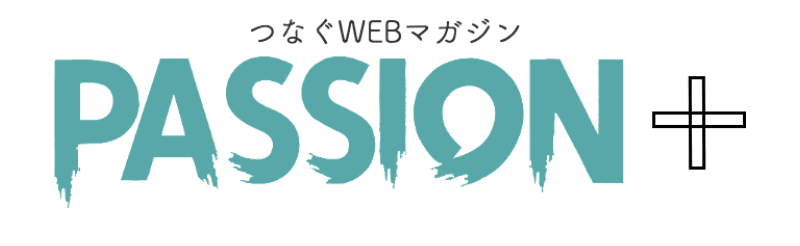COMPANY
(注意)本記事は、金剛株式会社が1991年8月10日に発行した機関誌「PASSION VOL.8」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。
本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。
(1)経済の成熟化に伴う消費傾向の変化
GNPが如実に現れる個人消費は、経済史でも類を見ない伸びです。少量多品種、利便性追及の傾向が顕著で、物流形態は小口多頻度配送になっています。しかし、この過熱する傾向は、人手不足という現実に明らかに逆行します。また交通渋滞は、環境問題の高まりと共に批判の声が強まり、行政側も無視できない状況です。更にコストの慢性のUP、経費負担の増加など数々の矛盾が発生し、小口多頻度配送は現在岐路にあります。既に各地でこのシステムが変化しつつあるとも言われています。
(2) 人手不足・高齢化社会への移行
人口問題は急激に変化しています。すでに出産率は約1.5人となり、急速な社会の高齢化が進行中で、労働力のバランスに大きな影響を与えています。 高生産性の資本集約型産業や、いわゆる”イメージの高い” “カッコ良い”企業などには若年労働力が集中し、低生産性の労働集約型産業や中小の卸小売業・物流業界は労働力の確保が難しくなり、いまや社会的課題として対応を迫られています。
(3) 女性の社会進出
この現象は(2)とも密接に関連します。深刻化する労働力の補填として、女性の社会進出が活発になっており、出産率低下による育児期間の短縮・家事省力化機器の利用・高学歴化・晩婚化など様々な条件が、女性の就労時間延長に更に拍車をかけています。 主婦労働力はパートタイムに、若年女子労働力は人材派遣の形で企業内に入る新しい傾向が生じ、恒久雇用にかわりパートタイム雇用が増えつつあります。やはり労働力は資本集約型産業に集中、小資本の企業では労働力が不足するという摩擦が生じています。
以上のような環境の変化に伴い、物流業務にも様々な変化が生じています。例えば、最近では共同配送をシステム化しようという動きが活発です。共同配送は、企業間の思惑・利害など数々の障害があり、一朝一夕には確立できないシステムですが、将来の物流を決定付ける重要なポイントでしょう。またPOS (Point of sales) システム、バーコードシステムの利用による物流ラインの管理なども、その効果を大きく期待されています。
この様に物的流通を、単なる物の流れとしてではなく、生産時点から販売時点までを一貫したシステムとしてとらえ、よりシビアに分析する必要が生じています。守りの経営から攻撃の経営へ。市場環境の変化にフレキシブルに対応できるシステム作りとは、経営目標に合致する効果的な物流システムを作り出すことに他ならないのです。
(参考文献)
日経ロジスティクス 日経BP社
省力と自動化 オーム社
MH ジャーナル 日本MH協会
無人化技術 通研究社
自動化技術 工業調査会
(株)日立物流 営業案内
(株)日立物流福岡営業所 営業案内
日立物流、和白配送センターご案内 HB-TRINET 21世紀への物流システムの構築
オフィス移転システム ((株)日立物流引越センター)
(株)正興商会 会社案内
(1991年8月10日刊行)